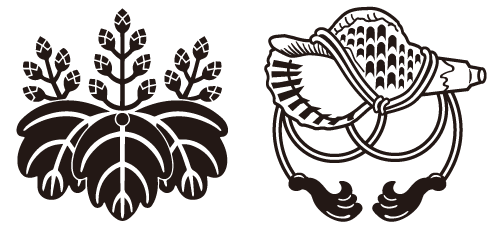月のたとえ。〜寒露
中秋の名月、そして十六夜も過ぎて
昨日は二十四節気の第十七番目の寒露(かんろ)を迎えました。
旧暦では九月節(八月後半から九月前半)にあたり、
朝方はさらに冷え込み、冷たい露が草木を濡らす季節。
早朝、仏飯などで外に出ると身体が寒さで縮こまります。
いよいよ本格的な寒さを迎える少し手前。
とは言っても日中は行楽に適した、過ごしやすい気温ではあります。
現在は台風の影響で曇り空の日が続いていますが、
昨晩は久しぶりに美しい月が顔を見せ、夜空を煌々と照らしていました。
月は毎日その姿を変えながら、雲の陰に隠れていても、
確かにそこに輝き続けている。月や星や太陽もそういうもの。
太古の昔から地球とともにあり、見る者の心にさまざまな感情や
祈りも映してきたでしょう。
私自身、子どものころは夜空を見上げるのが大好きで、
あまりに長く見ていて首が痛くなり、頭に血が上って
終いに気分が悪くなりゲボしたのを覚えています(笑)。
さて、この月という存在は、どこか心を惹きつける力を持っています。
そして仏教の教えの中にも月はたびたび登場します。
瞑想法の一つ月輪観にも見られるように、月は清浄な悟りの象徴とされ、
また多くの譬え話にも用いられています。
その中でも、私が好きなものに龍樹菩薩の大智度論に説かれる
「指月の譬(しげつのたとえ)」があります。
ある人が、相手に月を見せようとして指さしたところ、
その人は指ばかりを見て、肝心の月を見ることができなかった。
この話が教えているのは、
手段に気を取られて目的を見失ってはいけないということ。
私で言うなら、どれだけ経典を読み、仏教書で学び
偉い先生の勉強会に参加して話を聞いたとしても
なぜそれを学んでいるのかを見失えば、この指を見ていると同じこと。
さらに言えば、学んだだけでわかったような妄想と
頭でっかちになってしまえば、もっと悪い。
大切なのは、釈尊が説かれた真理という月を見ようとする心。
この教えは、仏教に限った話ではなく、
私たちの日常や人間関係の中にも通じます。
言葉や形、表面だけにとらわれず、その奥にある心や真意を
見ようとする姿勢こそが、月が静かに教えてくれた
大切な気づきなのかもしれません。
合掌