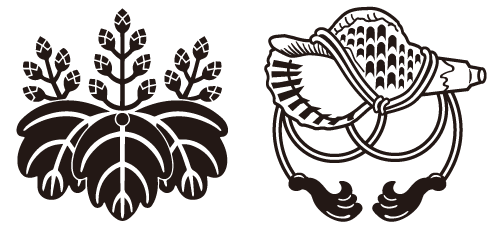お盆とご供養の心
8月2日より、お手伝い先の寺院さまのお盆参りに
順次伺わせていただいております。
一般的に「お盆」とは8月13日(迎え火=盆の入り)から
8月16日(送り火=盆明け)までの4日間を指します。
一部の関東地域では、明治時代に旧暦から新暦へ移行した際、
当時の政府の方針に従い、新暦7月15日を中心に
お盆を行うようになりました。
これにより、現在でも東京やその周辺などでは、
7月13日~16日をお盆とする「新暦7月盆」が行われています。
さて、お檀家さまや信徒さまのお宅をお参りしていると、
この時期はさまざまなご質問をいただきます。
特に多いのが仏壇の祀り方や宗派の違いに関するものです。
たとえば
「お嫁さんのご両親が他界し、一人娘なのでご実家のお位牌だけでも持ってきて供養したい。でも、宗派が違う。ひとつの家に宗派の違う仏壇や位牌を置くと、ご先祖同士が喧嘩して災いが起きると聞いたことがあるが、大丈夫なのか?」
こうしたご相談は、実際によく耳にします。
結論から申し上げますと
同じ家の中(同じ姓のもと)で他家の仏壇や位牌を安置することには、
何ら問題はありません。
宗派の違いはあっても、仏教の根本はお釈迦さまの教えであり、
その大元は同じです。時代の流れや教義の解釈の違いによって
多くの宗派が生まれましたが、その本質は「いのちを尊び、敬う心」です。
そして、災いなど起こるはずもなく、
先祖が子孫を苦しめるようなことは決してありません。
ご先祖様は、常に子孫の幸せと安寧を願ってくださる存在だと思います。
そして、何より大切なことは
今を生きる私たちが、真心からご先祖や亡き方々をご供養すること。
その心が、私たちの中に慈悲の心を育み、その廻向は巡り巡って、
私たち自身の積善へとつながっていきます。
もちろん、ご先祖様や亡くなられた仏さまを敬うことは大切です。
しかし同時に、日々の暮らしの中で他者への思いやりを忘れないことも、
同じくらい大切だと思います。
「私が苦しみを持っているように、他者もまた苦しみを抱えている 」
そうした共感と寄り添いの心こそが、仏教の実践そのものであり、
日々の供養の根幹だと感じております。
合掌