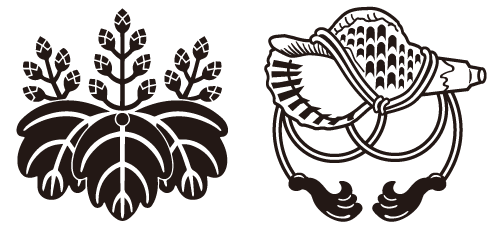大暑によせて 〜二十四節気とは〜
さて本日は「大暑(たいしょ)」
一年のうちで最も暑さが厳しいとされる時節を迎えました。
この大暑を境に、次の節目である立秋の前日まで、
暦の上では最盛の暑さが続くとされています。
近年は昔と比べて気温もぐんぐん上がり、
猛暑や酷暑といった言葉をよく耳にするようになりました。
私が子どもの頃などは、30度を超えたら
「今日は暑いねえ、猛暑だね」などと話していたものです。
夕方のゲリラ豪雨などを見ても、
日本の気候が徐々に亜熱帯へと変わってきているのかもしれません。
春と秋が短く感じられるという声も、近年は本当によく聞きます。
もっとも、こうして気候の話をしても、暑い暑いといくら言っても
暑さが和らぐわけではありませんが(笑)
これから夏祭りや花火大会、海水浴など、
レジャーや外出の機会が増える時期でもありますが、
どうか水分をこまめに摂り、自宅であってもエアコンを上手く使って
熱中症などには十分お気をつけてお過ごしください。
さて、こうした日本の季節の移り変わりを、
古来より丁寧に表してきたものに
二十四節気(にじゅうしせっき)があります。
これは一年を春夏秋冬の四季に分け、それぞれをさらに六つずつ、
合計24の節目として捉える暦法です。
たとえば「立春」「夏至」「冬至」など、
皆さまも耳にされたことがあると思いますが、
これも二十四節気の一つです。
この節気の名称と時期は、実際の気候の変化を非常に的確に表しており、
特に農業に携わる方々にとっては、
いまもなお大切な指標として暦に目を通されていることが多いのです。
以下に二十四節気を季節ごとにご紹介いたします。
それぞれの言葉に、日本人が大切にしてきた自然との関わりや、
生命いのちの循環へのまなざしが感じられます。
春:
立春(りっしゅん)、雨水(うすい)、啓蟄(けいちつ)、
春分(しゅんぶん)、清明(せいめい)、穀雨(こくう)
夏:
立夏(りっか)、小満(しょうまん)、芒種(ぼうしゅ)、
夏至(げし)、小暑(しょうしょ)、大暑(たいしょ)
秋:
立秋(りっしゅう)、処暑(しょしょ)、白露(はくろ)、
秋分(しゅうぶん)、寒露(かんろ)、霜降(そうこう)
冬:
立冬(りっとう)、小雪(しょうせつ)、大雪(たいせつ)、
冬至(とうじ)、小寒(しょうかん)、大寒(だいかん)
自然に寄り添いながら暮らすこと。
今日この日が、縁起の法に則って尊いめぐりの中にあると感じられること。
仏教の教えもまた、そのような感覚と深くつながっているように思います。
暑さにご自愛いただきながら、よき夏のひとときをお過ごしください。
合掌
伊達市梁川町。当院の地域は本日も全国2位の暑さです‥