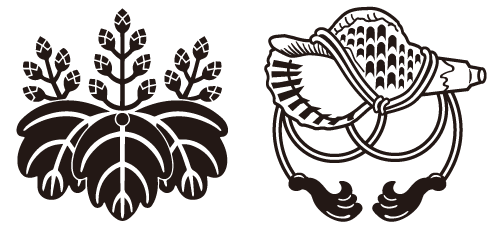私と准胝観音さま、そして僧侶の道へ
前回、准胝観音さまの小仏像を
師僧のお寺にお持ちしたところまでお話ししました。
今回はその続きとして、私が仏さまとのご縁を通じて、
僧侶の道へと歩み始めた経緯を記してみたいと思います。
実際にお寺へ伺う前、私はまずお電話にて
住職様にこれまでの経緯をお伝えしました。
このお像をきちんとしたかたちでお祀りしたいこと、
ご性根を入れて頂き、お線香やお経をお供えして
きちんとお参りができるようにしたい。そんな思いをお話ししました。
後日、お寺に伺うと、住職様はご仏像をご覧になり、
「これはやはり中国や東南アジアのタイプの准胝さまだね」と仰いました。
丁寧に作法を整え、観音経をお唱えし、表白を読み上げて、
厳かに開眼供養を執り行ってくださいました。
それまで私は、親戚の法事や葬儀などでお寺に行った経験はありましたが、
自分のためにこのようなかたちでお寺と関わるのは初めてでした。
この時初めて知ったのは、こちらのお寺が檀家寺ではなく
信者寺であるということ。つまり、祈願を中心に活動されている
お寺であることに、私は新鮮な驚きを覚えました。
堂内は荘厳な雰囲気、読経の声と力強い太鼓の音が響き、
まるで私自身を励まして導いてくれているように感じました。
儀式が一通り終わり、お茶を頂きながら住職様とお話している中で、
今も心に残っているお言葉がありました。
「お経をあげたり、お線香を手向けたりすることはとても良いこと。
でもね、あまり拝みすぎるんじゃないよ」と。
最初はその意味がよく分かりませんでした。
けれども時が経つにつれ、まるで私が僧侶の道に進むのを
予測していたかのような、その言葉の中には私が間違った道に
進まぬ様にとの注意の意味もあったのだと思います。
自宅に戻ってからは、嬉しさのあまり、毎日お線香をあげ、
あの時お唱えしていただいた「観音力……」というお経が
どうしても自分でも唱えたくなり、ネットで調べるうちに
それが観音経であることも知りました。
すぐにAmazonで取り寄せ、そこからは観音経や般若心経を
唱えることがすっかり私の日課になっていきました。
毎朝には氏神さんをお参りに行って、仕事が休みの日には
市内の神社仏閣を巡り、休憩中には近所の図書館で仏教の
書物を読み漁るような生活となっていきました。
そんな日々が数ヶ月続いていくうちに
私ははっきりと僧侶になりたいと思うようになりました。
それはなぜか?
仏教の教えや、お釈迦さまのお言葉、先人の僧侶方の逸話などを通して、
たとえ現実は何も変わらなくても、自分の心が変わる。
そのありがたさを実感できたからです。
現実的な悩みは消えていないのに、それをどう受け止めるか、
どう考えるかが変わったことで、心がとても軽くなったのです。
そしてあんなふうに堂内でお経を唱えられるようになりたい。
そんな憧れにも似た気持ちも実際あったように思います。
私は調べ始めました。一般家庭出身の自分でも僧侶になれるのか。
真言宗には本山の修行道場があり、
そのひとつが以前お像を開眼して頂いたお寺が所属する真言宗醍醐派。
調べるうちに伝法学院という道場があることを知り、
また高野山の専修学院、仁和寺の密教学院といった
他にも道場があることも知りました。
おのずと真言宗で進みたいという思いが固まっていったのだと思います。
それぞれの本山にに緊張しながら電話をし、費用や手続き等、
それ以前に先ずは師僧となっていただける僧侶を見つけなければ
何も始まらない事も教えていただきました。最初の難関ですね。
そして2011年の1月、小正月を過ぎた頃、再びあのお寺にお電話をして
「ぜひ一度、相談があるのでお話を聞いて頂きたい」とお願いをしました。
そして、住職様に直接、
「僧侶になりたい。ぜひ弟子にして頂けないでしょうか」と
お願いしました。住職様は冷静に話を聞いてくださいましたが、
きっと内心ではとても驚かれていたと思います。
私の過去や家庭のこと、生き方、どうして僧侶になりたいのか。
そういったことを淡々とお話ししていくうちに、
住職様から「あなたのお母さんにも会ってみたい」と言われました。
このひとことが、とても嬉しかったと同時に大きな転機となる一言でした。
実は私は生後4ヶ月で現在の両親のもとに養子縁組にて迎えて頂きました。
実母には今も会ったことがなく実父はさらに誰なのかすらも分かりません。
そんな私を本当の子供のように、あるいはそれ以上に大切に
育ててくれた母。けれど私は両親に反抗し、迷惑をかけ、
ついには戸籍からも除籍されて10年以上も縁を切ったままでした。
それでも母は、「本気でそう思っているなら、お母さんは反対しない。
でも、お坊さんになるなら、もう帰ってこない覚悟で修行に行きなさい」と
言ってくれたのです。電話のあと、私は涙が止まりませんでした。
後日、母とともに山形へ向かい、住職様と奥様にお会いしました。
変わらぬ旨をお伝えし、最終的に母の思いも伝わったのだと思います。
正式に徒弟となる話がまとまりました。
僧名は「准庵」じゅんあん。准胝さまの一文字をいただき
庵(あん)は(いおり)とも読みます。意味は僧尼が住む小さな家。
組み合わせると色んな意味に取ることができます。
何ともありがたい名前を付けていだだきました。
当時、私は38歳。母は68歳。
親というのは、子どもがいくつになっても親であり、
子を思う気持ちは変わらないとよく言いますが、
この時ばかりは心底、母親という存在に
ただただ有難さだけがどっと押し寄せました。
私はいつも思っています。母親の思いはまさに准胝観音さまだと。
そして2011年5月に醍醐山伝法学院に入学するわけですが、
その2ヶ月前には死者行方不明者、あわせて2万2228人という
東日本大震災という歴史に残る大災害が東北を襲いました。
多くの方々が本当に大変な辛い思いをされた年。
私にとっても大きな区切りであり、
新たにスタートをきる年となりました。
合掌