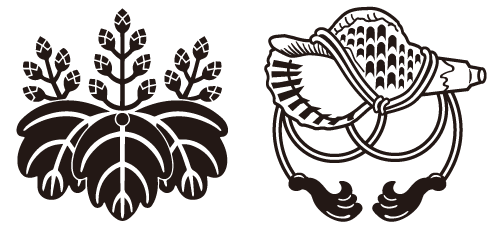八朔(はっさく) 旧暦八月一日のお話
「八朔」と聞くと、多くの方がまず思い浮かべるのは
果物の八朔ではないでしょうか。ご多分に洩れず、私もその一人です。
今日は、果物ではなく暦のお話を少しだけ。
旧暦の八月一日は「八朔(はっさく)」と呼ばれ、
暦の上では一つの節目とされる大切な日です。
この日は、田んぼの稲をはじめとする
農作物の豊作を祈願したり、やがて収穫を控えた時期に
田実(たのみ)の祝いとして新穀を贈り合う習わしが生まれました。
この風習は、もともと農村の中で広まっていたものですが、
次第に公家や武家、町人の間にも伝わり、
八朔の憑(たのもの)と称して、
さまざまな物品を贈答するようになったそうです。
現在、夏のご挨拶として親しまれているお中元の風習も、
この八朔の文化に由来しているとも言われています。
自然の恵みに感謝し、人と人とのご縁を大切にする。
暦を覗いてみるとそんな日本の美しい風習がたくさんあります。
今もなお私たちの暮らしの中に息づいていることを、
改めて感じさせてくれます。
合掌
以下、世界大百科事典より引用
旧暦8月1日(朔日)のこと。重要な節日で,八朔節供,田実(たのみ)の節供などといわれ,稲の収穫を目前にしての豊作祈願や予祝に関したこと,および各種の贈答(贈物)が行われる。八朔盆といって盆月の終了を意味する伝承もある。西日本各地にはタホメ,サクダノミなどと称して田に出て作柄を褒めてまわる予祝儀礼があるし,稲の初穂を神に献じる穂掛けの儀礼をする所が全国に点々とある。香川県など瀬戸内には馬節供といって新粉細工や張子の馬を男児誕生の家へ贈ったり,関東地方には生姜節供といってショウガを持たせて嫁に里帰りさせる所がある。これら贈答の習俗は上流文化の影響というが,室町時代に盛行した〈たのみ〉〈たのも〉などという進物を贈答し合う風は,農村に基盤をもつ武家の風が取り入れられたものといわれ,農作を助け合った間柄で,神供としての田実,すなわち初穂などを贈り合ったことに源があるのではないかとされている。豊作祈願と風祭をかねて宮籠りをする所や嫁の里帰りの日とする所もある。八朔を昼寝の終期,夜なべの初日とする所の多いのは,これ以後が本格的な収穫期に入るからだろう。
→憑(たのみ)