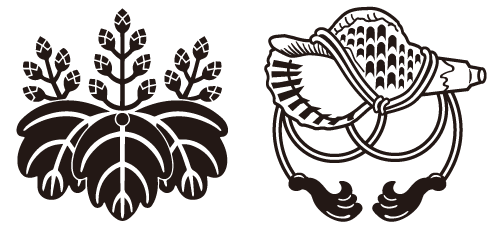立秋のお話 〜季節の移ろいとお盆のこころ
お盆参りの真っ最中ではありますが、二日間の中休みをいただき、
今日まで少しお休みを頂戴しておりました。
さて、今日は立秋のお話を少し。
「秋の気立つなり(あきのきたつなり)」
立秋とは、暦の上で秋の気配が立ち始める頃を指します。
実際には一年で最も暑い時期にあたりますが、
この日を境に「残暑」という言葉が使われ始めます。
今年(令和〇年)は8月7日が立秋とされておりましたが、
もともと二十四節気というのは「日付」そのものではなく、
ある一定の「時期」や「期間」を表すものです。
立秋の期間は、8月7日頃から8月22日頃までとされます。
この立秋は、二十四節気の中でも特に重要な
八節(はっせつ)のひとつに数えられます。
八節とは以下の通りです:
二至:夏至・冬至
二分:春分・秋分
四立:立春・立夏・立秋・立冬
この二至二分四立を総称して八節と呼び、
古くから季節の区分や農作業の目安として、
また生活の節目としても大切にされてきました。
また、節分とは本来、この四立の前日を指す言葉で
季節の分かれ目を意味します。
現在では2月の節分が広く知られていますが、本来は年に4回あるのです。
そして、この立秋の頃は、さまざまな行事が集中する期間でもあります。
中でも「お盆」は、ご先祖様が浄土から戻られるとされる特別な期間です。
もともとは、仏教伝来以前の神道における
農耕儀礼や祖霊信仰が背景にあり、
それが仏教と融合して、今のような形になったと考えられています。
このお盆の時期には、七夕祭り、盆踊り、夏祭り、花火大会、お中元など、
さまざまな風習や行事が行われますが、
いずれもご先祖様を迎え、祀り、感謝を捧げる心から
生まれたものだとも言われています。
厳しい暑さが続く中ではありますが、自然の移ろいを感じ、
仏さまやご先祖様への想いを深めるこの時期を、
心静かに過ごしてまいりたいものです。
合掌