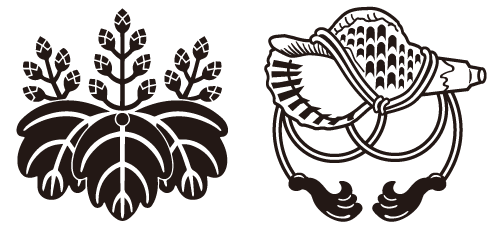仏教の中の神々
以前、仏教における神々や神仏習合について少し触れましたが、
今日はその続きを書きたいと思います。
神という言葉から連想するもの
皆さんは「神さま」と聞いて、何を思い浮かべますか?
きっと近くの神社や、西洋のキリスト教、またイスラム教などを
連想される方が多いでしょう。
その際、神さまには次のようなイメージが持っていると思います。
神=人智を超えた、全知全能の絶対的な存在。
人格を持ち、人間に感情を向け、すべてを司る存在。
これはきっと一神教における神のイメージからでしょう。
一方、日本の神々はどうでしょうか。
いわゆる「八百万の神」と呼ばれるように、山川草木、自然現象、
あらゆるものに神が宿るとする考え方です。
これはアニミズム的な土着信仰に基づき、多神教的な性格を持っています。
きっと日本の風土だからこそこういった思想が育まれてきたと思います。
さて、仏教が日本に伝来して間もなく、日本古来の神々と仏教の仏が
結びつく神仏習合という現象が各地で起こりました。
これは仏教が本来持つ包括的で普遍的な性質と、
日本の八百万の神という多神教的な考え方が、
とても相性が良かったためと思われます。
インドでも土着の神々が仏教に取り入れられており、
日本においても自然に習合が進んでいきました。
特に密教が鎮護国家のために国家的に重視されると、
神仏習合は急速に広まり、本地垂迹(ほんじすいじゃく)
という考えが定着しました。
これは日本の神々は衆生を救うために、
仏や菩薩が仮の姿で現れた存在であるという考えです。
例えば「権現」という神号も「仮に現れた」という意味を持ちます。
有名な例を挙げると、伊勢神宮の天照大神は本地仏が大日如来とされ、
熊野三山では本宮が阿弥陀如来、新宮が薬師如来、那智が千手観音とされ、
これを熊野三所権現と呼びます。
このように、明治の神仏分離令が出るまでは神と仏は同体である。
という考えは当たり前であり、神社には神宮寺が建てられ、
寺には鎮守の社が祀られることが多々ありました。
そして仏教における神の位置づけです。
ここで大切なのは、仏教における神の基本的な捉え方です。
仏教には一神教的な絶対神という概念は元から存在しません。
仏教で説かれる神とは、私たち人間や動物と同じく
六道輪廻の中を生きる迷いの衆生であり、
地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天、これを六道と言い
そのうちの天(天界や天部という)の衆生であります。
例えば梵天・帝釈天・四天王といった諸天、
堅牢地神、龍王、火天などの善神、
あるいは夜叉・羅刹といった鬼神も、すべて輪廻する存在です。
とは言っても神は神通力をもっており
私らが想像できないほど長い寿命をお持ちなのです。
まさしく人とは天地の差という言葉がぴったりです。
しかし最後に待っているのは死。神といえども逃れることはできません。
この中には、過去の業によってその身を得た「業報の神」と、
仏や菩薩が衆生を救うために仮に神の姿を取った「垂迹の神」
とがあります。彼らは仏法を守り修行者を守護しながら
様々な方便を使い助けることはできますが、自らも迷いの中にあるため、
六道輪廻を超えて衆生を解脱させる力は持ちません。
そのためお釈迦さまは、神を修行の対象として拝んではならないと
説かれました。ここで大切なのが仏教の「因縁果」という教えです。
すべての出来事は「因(原因)」があり、「縁(条件)」が整ったとき
「果(結果)」が生じます。
例えば、菜の花の種が土に落ちる(因)、
そこに雨や日光が与えられる(縁)、すると菜の花が咲く(果)。
このように、結果は偶然ではなく必然であり、
決して神の意志によって決まるのではない、
というのが仏教の基本的な見方です。
つまり、仏教における神は、私たちと同じ輪廻する存在であり、
絶対的な支配者ではありません。
そして神仏習合という日本独自の信仰の歴史を経て、
神と仏が共に祀られ、人々の心を支えてきました。
神も仏も結局は「縁」によって私たちとつながり、
その存在を通じて因果の道理を学ぶことが大切なのだと思います。
合掌