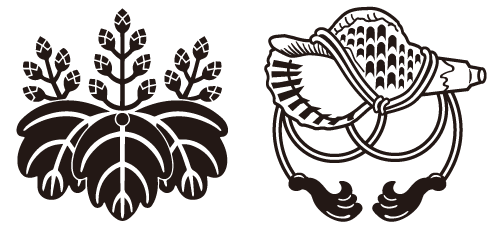観音様は変身上手
さて、夏から秋へと移ろい、早くも九月に入りました。
昨晩は久しぶりに恵みの雨が降りましたが、
今朝には止み、日中はだいぶ暑さが和らいだとはいえ34℃。
それでも秋田など各地では線状降水帯による河川氾濫の被害で、
大変な思いをされている方が多くいらっしゃいます。
被災地の皆さまが一日も早く、平穏な日常を取り戻せますよう
心よりお祈り申し上げます。
さて、先日信者さんから「観音経」についてご質問がありました。
観音経とは『法華経』の第二十五品
「観世音菩薩普門品(かんぜおんぼさつふもんぼん)」のことです。
その方は、普段ご自宅で般若心経をお唱えしており、
最近は観音経にも挑戦されているそうですが、
その中で同じ言葉の繰り返しのなかに梵王、帝釈、毘沙門、婆羅門婦女など
さまざまな名前が出てくる箇所があるのですが
あれはどういった意味なのか教えてほしいとの事でした。
私はとても良いところに気づかれましたねとお答えしました。
実はそこが観音経のクライマックスとも言えますし
観音様が観音様たる大切な場面なのです。
無尽意菩薩が仏に尋ねます。
「世尊、観世音菩薩はどのようにしてこの娑婆世界を行じ、
どのように衆生を救われるのですか」と。
するとお釈迦さまは答えられます。
「観世音菩薩は、仏の姿を必要とする者には仏の姿となり、
声聞の姿を必要とする者には声聞となり、
あらゆる姿に応じて現れ、説法し救うのである」と。
つまり、観世音菩薩は三十三のお姿を自在に現して
衆生を救ってくださるのです。
これがいわゆる「三十三身」であり、西国三十三観音霊場や
「三十三年に一度の秘仏御開帳」といった風習も、ここに由来します。
具体的には次のように分類されます。
三聖身 … (三つの聖なる身体)
1仏身、2辟支仏身、3声聞身
六種天身 … (六種の神々)
4梵王身、5帝釈身、6自在天身、7大自在天身、8天大将軍身、9毘沙門身
五種人身 … (五種類の人間の身体)
10小王身、11長者身、12居士身、13宰官身、14婆羅門身
四部衆身 … (僧侶や在家信者)
15比丘身、16比丘尼身、17優婆塞身、18優婆夷身
四種婦女 … (四種類の女性)
19長者婦女身、20居士婦女身、21宰官婦女身、22婆羅門婦女身
童男童女二身 … (二種の子供)
23童男身、24童女身
八部衆身 … (八種類の仏教を守護する神々)
25天身、26竜身、27夜叉身、28乾闥婆身、29阿修羅身、30迦楼羅身、
31緊那羅身、32摩候羅迦身、
33執金剛身一身
観音さまは、どんな人であっても、その人にとって、
いま一番ふさわしい姿となり、国や時代、
生まれや立場に関係なく、名を呼ぶ者を必ず救ってくださる。
これが観音経の大きな教えです。
少し余談ですが、私が子どもの頃に流行ったアニメ
「キューティーハニー」を思い出しました。
きっと私の年代しかわからないかもしれません‥。笑
必要とされる姿にパッと変身して活躍するところは、
観音さまのお姿と少し似ているように思います。
もっとも、観音さまをセクシーなヒロインと同一視すると叱られそうですが
イメージとしては近いかもしれませんね。笑
観音経は確かに長いお経ですが、観音さまのお力と慈悲を知るうえで
とても大切な経典です。興味を持たれた方は、多くの解説本もありますので
手に取って読まれるのも良いでしょう。
今後、私のブログでも少しずつ、観音経について分かりやすく
解説していければと思っています。
ちなみに、当院の朝のお勤めでは、(毎朝7:00〜)
般若理趣経をはじめさまざまなお経をお唱えしておりますが、
准胝さまの『仏説七倶胝仏母心大准提陀羅尼経』は毎朝。
さらに朔日、8日、14日、15日、18日、23日、24日、28日、29日、30日
には、観音経全段をお勤めしております。
私も大好きなこの観音経ですがこの機会に皆様にも
少しでも興味を持って親しんでいただければと思います。
合掌
新しく奉納頂きました幟旗(青紫)は先月28日より設置いたしております。